こんにちは。にのじです。
今回は、ベランダビオトープの作り方を紹介します。
普通の水槽を立ち上げるよりも導入コストが安いのに、楽しめるポイント満載なのでぜひ試してみて下さい。

我が家のビオトープについては別記事にて紹介しています。
ベランダビオトープの作り方
前提
- 初期投資を抑える
- メダカが元気に生きられる環境を作る
材料
- 発泡スチロール箱
- 赤玉土
- 水
- 水草
- メダカ

メダカを入れるのは環境が整ってからにしましょう!
- カルキ抜き
- 牡蠣殻(カリウム液肥でもOK)
にのじ流 ビオトープの作り方
発泡スチロール箱に赤玉土を入れます。メダカの泳ぐスペースをある程度確保するため、あまり入れすぎない方が良いと思います。多くても箱の高さの3割程度で充分です。

濾過装置を設置しないビオトープでは全ての栄養分を水草に吸収してもらう必要があるため、ほとんど栄養分を含まない赤玉土を推しています。

大量に必要な場合はネットで買った方が安いし、運ばずに済むので楽という説もあります。
水を入れます。赤玉土から細かい泥が溶け出してとても濁るので、軽く揺らしてから泥水を捨てます。

再度水を入れます。立ち上げ当日に生体を入れる場合はカルキ抜きした水が必要ですが、そうでない場合はひとまず水道水でも屋外放置でカルキが抜けるため問題ありません。

家に水質の安定している水槽がある方は、バクテリアの定着を早めるために飼育水を入れることをオススメします。また、底床を赤玉土にすると水質が弱酸性寄りになります。メダカは中性〜弱アルカリ性の水を好むので、牡蠣殻やカリウム液肥などを少しずつ入れることでpHを上げましょう。
ビオトープ内のカルキが抜けたらメダカをお迎えしましょう。お店で眺めて買うも良し、メダカ掬いに参加するも良し、所有者の承諾のある田んぼでガサガサするも良しです。まだ入れていなければ水草も調達しましょう。

ミナミヌマエビやヒメタニシなどのお掃除要員を同時にお迎えしてもOKです。
水草を入れ、水合わせをしてからメダカを導入すれば完成です。牡蠣フライをおつまみにビールでも飲みながら眺めて一息つきましょう。


まとめ
いかがでしたでしょうか。難しい工程はないので敷居は低いと思います。まずはこの発泡スチロール箱からスタートして、本腰を入れる気になったら徐々に睡蓮鉢などを買い揃えて本格的なビオトープへと進化させていくのも楽しそうです。その際は今回省略したレイアウト素材(岩や流木など)と苔などを組み合わせてみたいものです。
今回は以上です。

不明点があればお気軽にコメント下さい。(わかる範囲で)お答えします!
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
それではまた!
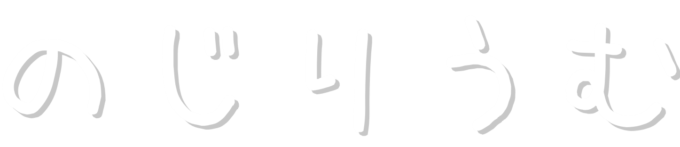















コメント